導入事例
2025.01.14
東多摩再資源化事業協同組合、加盟10社・109台に導入――1年で事故「半減」、一時不停止も「4分の1以下」に

東京都東村山市・小平市・西東京市・東久留米市・清瀬市・東大和市の6市を事業範囲とする東多摩再資源化事業協同組合。各市より委託を受け、新聞・雑誌・段ボール・古布などの資源物を回収し、保管するヤードへの受け入れ、リサイクルセンターでの選別作業などを行っています。
同組合には地域でリサイクル事業を営む10社が加盟し、再生資源物(古紙・古布・金属類・ビン・缶等)を回収・再資源化。さらに自治会や福祉団体などとタッグを組み集団回収の推進や、リサイクル知識の普及のための社会貢献活動など幅広く取り組んでいます。
さらに、官公庁の委託を受けるにあたって官公需適格組合を関東地区で第1号の認証を受け、品質管理と業務の適正化に努めている他、持続可能な社会の実現と組合の運営に関わる環境負荷の低減のため、東村山市が進める『SDGsパートナーシップ』にも参加し、環境にやさしい組合運営に努めています。
資源回収に必要となるのが「パッカー車」と呼ばれる回収車や、2t~3.5tのトラックで、日々の作業のために活用する車両は同組合で109台。回収は地域の生活エリアとなるため狭い道や行き止まりのある道を通ることも多く、「安全・安心」を守るため『DRIVE CHART』を2023年12月に全台導入しました。
導入の理由、運用やその成果について、東多摩再資源化事業協同組合専務理事で、同組合の加盟社である三栄サービス代表取締役社長の紺野琢生さんにお伺いしました。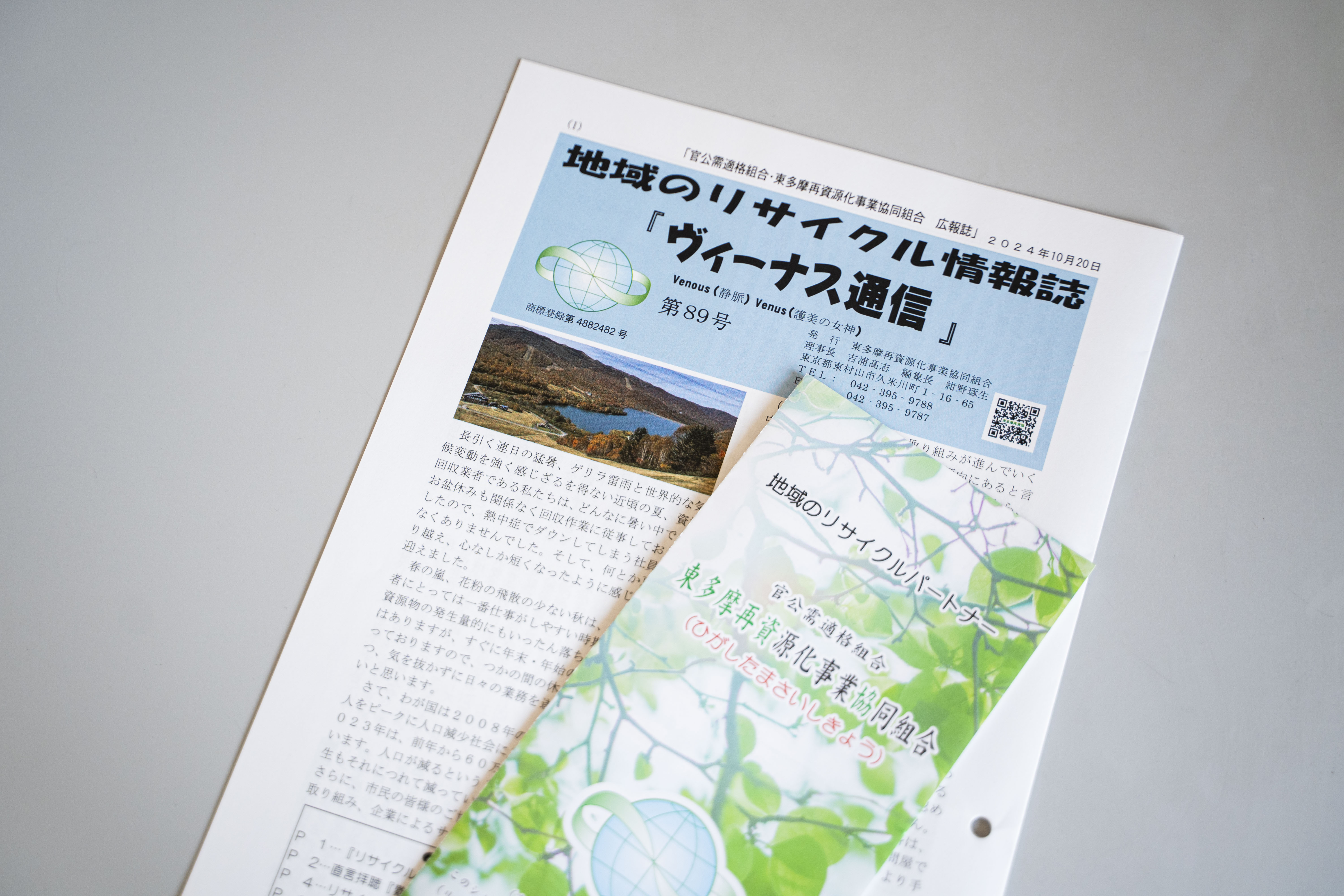
組合名 東多摩再資源化事業協同組合
業種 再生資源物(古紙・古布・金属類・ビン・缶等)を回収・再資源化する事業者組合
保有車両数 109台
導入時期 2023年12月
導入目的・課題
・資源回収車だからこそ、住宅街の狭い道などリスクが高い場面が多かった
・毎日稼働する車両のドライブレコーダー映像を、日常的に確認するのは難しかった
・ドライバーを加害者にも被害者にもさせないよう事故から守るため
導入後の取り組み
・「脇見」「一時不停止」は特にゼロを目指し、警報付きのリスク運転は帰庫時に即確認
・週次サマリーメールの数値をグラフ化し加盟各社に提供、指導に繋げてもらう
・加盟社の代表者が集まる「業務委員会」にて、組合全体や各社で出た成果を共有
導入効果
・導入後1年で「一時不停止」は4分の1、「急後退」は3分の1に
・細かな物損事故を含めた事故件数も半減
社会を支える産業だからこそ「無事故無違反」の徹底が重要
――”SDGs”の文脈でも環境は注目を集めているかと思います、組合の活動としてはどういった点に力を入れているのでしょうか。
組合は30年以上、上部団体である東京都資源回収事業協同組合は70年以上、リサイクルの分野で事業を行っています。この分野は“静脈産業”と言い、生活財や消費財を生み出す動脈産業を陰で支え、再資源化によって再び社会に流通させています。
社会に必要不可欠な活動だからこそ、その作業品質にはこだわりを持っています。「官公需適格組合」、これは官公庁の委託業務をしっかり遂行できるという基準をクリアしたという資格でして、こちらを関東にて第1号で取得しています。
最近ようやく動脈産業の企業も“SDGs”や“環境”への取り組みと銘打って取り組みを始めています。この流れを活かすためにも、長年続けている我々の活動が高い水準で継続されることは重要だと考えています。
――資源回収車だからこそ意識している安全運転もあるのでしょうか。
我々の回収作業は、住宅街の狭い道や袋小路のような道を入っていくことも多く、カーナビが対応できないことも多い。たとえばバックで入っていって、回収しながら出てくる際など、普通の運転よりも運転リスクは大きいと考えています。
そのため『DRIVE CHART』導入前から、回収作業員に向けて年に1~2回の安全講習会を行っているのと、組合が指名した検査員が各社を周って、アルコールチェックや車検証の管理、車の整備のチェックなどを出庫前に検査しています。法律、コンプライアンスを守りながら安全運転で作業に当たりましょうと、周知していました。
運転する車両は、パッカー車やトラック。例えば、パッカー車はバックアイカメラが上についているので、後ろはしっかり見えています。ただ、車両の脇や高さに注意だよ、と。逆にトラックはバックアイカメラが下についているので、注意するポイントが変わってくる。そういった点を、講習会も内容をカスタマイズして伝えていました。
パッカー車
導入後1年で、一時不停止は「4分の1」以下に
――そういった中で、『DRIVE CHART』を知っていただき、導入いただいたのはどのような理由からでしょうか。
『DRIVE CHART』を導入する前に使用していたドライブレコーダーでは、正直言いますと何かあった時にチェックする事しかできていませんでした。加盟社10社、それぞれ10~15台が毎日稼働しているので、全部のドライブレコーダーをチェックすることは中々難しい。ですので、まずは、クラウドで保存できるタイプのドライブレコーダーを探そうというのがスタートでした。
調べていくうちに、AIが事故につながる危険な運転をしているかどうかを自動でチェックしてくれるものがあると聞き情報を集めました。3社ほどで比較検討している間に、組合で1件一時不停止が原因の事故が起こってしまって…。もっと早く入れておけばよかったなと。
この事故がきっかけとなって『DRIVE CHART』の導入を決めました。「『DRIVE CHART』は、まさに今回のような事故を防ぎ、皆の生活を守るためにチェックしてくれるもの。監視しているんじゃなく、被害者にも加害者にもなってほしくないから、皆を守るために入れるんですよ」と運転者の説得もしやすかったです。
――導入されてみて、どのような変化がありましたか?
特に顕著なのは一時停止に対する意識の変化です。組合が担当する地域では信号が無いような狭い道路が多いこともあって、一時不停止の検出は多く出ました。ただそれも『DRIVE CHART』直後の話で、一時不停止に対する指導を強化してからは、「停止線でしっかり停まるようになりました」と運転者が口々に言うようになりました。
組合としても、一時不停止と脇見はとにかく「ゼロ」にしようと掲げています。毎週送っていただいている週次サマリーメールを集計して、加盟10社ごとにグラフにしたものを送り、「これを元に指導してくださいね」と伝えています。「効果が出ている」ことが視覚化されるのはモチベーションになるようで、一時不停止は導入から1年弱で4分の1以下まで減っています。
今、相対的に目につくのが急後退です。奥まった路地や開発で出来たT字の道路などはすごく多く、そういうところでバックする際に注意する運転者と、そうでない運転者の違いが出てきます。これも導入して分かったところなので、各社には注意して指導するよう伝えていますし、安全講習会でもそうした事実を伝えるように工夫しています。
事故も導入前と比較して「半減」。安全運転による回収時間増もほぼ無し
――運用する上で決めているルールはありますか?
先ほどの週次サマリーメールを活用したグラフでの各社への共有は毎週行うようにしています。あとは当社では警報が鳴るようなリスク運転が出たら、必ずその日中に一緒に振り返るようにしています。覚えている間に振り返りができれば、動画で証拠がしっかりあるので指導も伝わりやすいですからね。
組合に加盟する各社については基本お任せしていて、毎週お渡ししているデータをもとに工夫していただいています。また毎月、加盟社の代表者が集まる「業務委員会」を組合で開催する中で、組合全体と各社のデータを配って、変化があれば全員で情報を共有するようにしています。
――改めて『DRIVE CHART』導入後、効果についてはいかがでしょうか?
皆さん本当に気をつけるようになって、導入前の2023年と、導入後の2024年で比較すると交通事故を半減させることができました。基本的に住宅街を走っており速度はそれほど出ていない状況なので、発生するのは細かい物損事故が多いのですが、そのような事故も減っています。
一時不停止は先ほど触れた通り4分の1以下に減っていて、急後退もその他のリスク運転が減っているために相対的に目につきますが、導入当初から見れば3分の1程度に減っています。講習や指導など導入前もかなり実施していましたが、数字として事故やリスク運転の減少が見えるというのはありがたいことです。
一時停止線できっちり停まることで、当初は“もしかすると回収の時間が余計にかかってしまうかな”というのが心配だったのですが、確認すると加盟10社中9社はほとんど変わりがありませんでした。安全運転に気を付けていても時間のロスが増えることは無いのだと再認識できたことも大きかったです。
顔認証、走行軌跡、ライブマップなど「車両管理機能」も活用
――車両管理の機能も活用していただいているんですね。
副次的なところでは「日報」という機能の走行軌跡の活用で、運転手が違うと同じ回収ルートでも1時間、2時間違うことがあるのが判明しました。業務効率の面でも事故防止の面でも、ルートは最適化しておきたい。回収の取り残しの電話が来ることもあるので、そういった際のチェックにも使っています。
車両の位置確認のために「ライブマップ」という機能も活用しています。たとえば、帰庫予定時間になっても帰庫していない場合の確認などには便利ですね。運転中は電話に出られないので、遠隔で確認できるのは助かります。また、ピンポイントの回収が入った時に“近くに車いないかな”とチェックしたりと活用できています。
あと、これは『DRIVE CHART』にした決め手のひとつですが、すごく便利なのは「顔認証」ですね。作業員は固定で使用する車というのがほとんどなく、今日はトラックで回収、明日はパッカー車で回収といったように車両が変わるんです。乗車するだけで、誰がどの車に乗っているか把握できるのはすごく管理しやすいですね。
回収された古紙
――『DRIVE CHART』導入いただいてまもなく1年経ちますが、周囲の反応や、今後の展望などはいかがでしょうか。
各市役所、公共施設、地元の皆様向けに『ヴィーナス通信』という機関紙を発行していて、リサイクルに関する様々な情報を発信しています。そこで『DRIVE CHART』について紹介したり、取り組みを周知したりしています。ある自治体の課長さんも「ウチの車両全台に入れたいな」と仰っていましたよ。同業者の方々に活用状況を質問されることも多いです。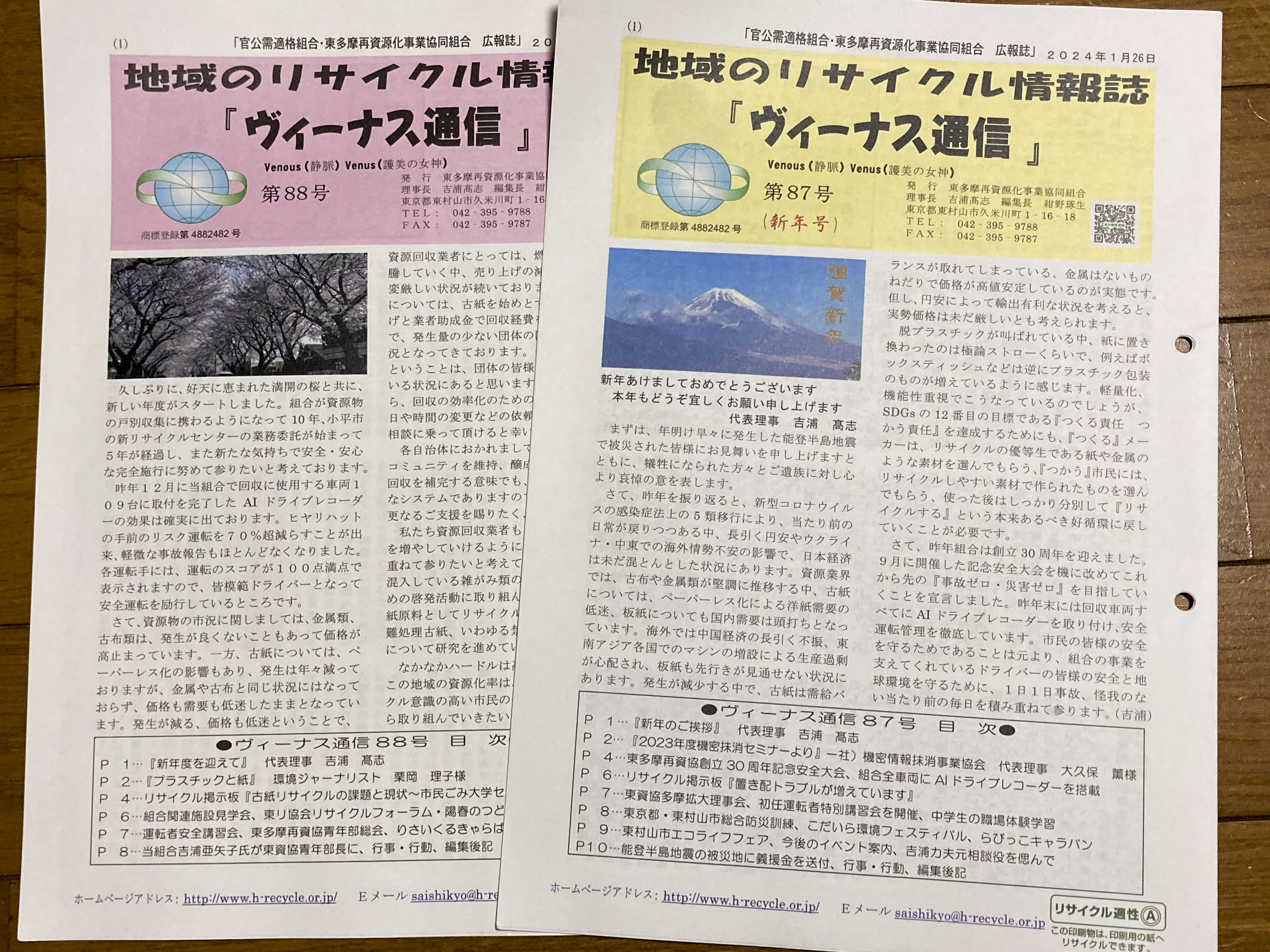
また、朝の体操のときに「あの道で一時停止線が薄くなっているから気を付けて」とか、『DRIVE CHART』のおかげで安全運転に関する話題が作業員同士のコミュニケーションとして出てくるようになりました。組合に加盟するどの会社さんと一緒になっても共通の話題になるので、その点は嬉しい活用のされ方だと思いましたね。
組合としては加盟10社、109台の車両を管理する責任がある。1日にいろいろな所で動いている車両を、『DRIVE CHART』ですべてチェックしてもらっているというのは、組合の経営サイドとしてもすごく安心・安全だと感じます。
過去、“社長が助手席に乗って安全運転かどうかチェックして下さい”と言われて、本当に確認したことがあるんです。でも、社長に間近でチェックされている時は、どうしても皆さん超がつくほどの安全運転になります。結局は同乗しても、普段の運転をチェックすることはできない。それが『DRIVE CHART』であれば、AIが検出してくれたものだけチェックすれば良い。コスト以上の価値を出してくれていると思っています。